
近年、アレルギー疾患の罹患率は増加しており、日本人の3人に1人はアレルギー疾患に罹患していると言われています。
アレルギー疾患を改善するためには、正しい予防・診断・治療法が必要ですが、年々、アレルギー疾患に対する医療は変化しています。
当院には、日本アレルギー学会にて認定されたアレルギー専門医・指導医7名とアレルギー専門看護師である小児アレルギーエデュケーター6名がおり、小児科と内科が一体となって、小児から成人までの様々なアレルギー疾患に対し、最新の知見に基づいた専門的医療を行っています。(現在、成人の新患患者さんは受け付けておりません)
正しい診断に重要となる食物負荷試験や運動負荷試験、アレルギーの根本的治癒を目指すことのできる免疫療法(減感作療法)なども行っております。
※ アレルギー科の診察を受ける際、初診の場合は事前の予約が必要です。
地域医療連携室までご連絡ください。
TEL (直通) :043-422-3025
(代表) :043-422-2511 内線 238
FAX (直通) :043-422-3437
受付時間 :8:30~17:15(土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)

診療実績 (2014年)
外来通院患者数:各月約700名
食物負荷試験:年間約500件
エピペン処方数:年間約220本
アレルギー疾患はよくみられる疾患ですが、それぞれの疾患をきちんとした検査や臨床症状に基づいて正しく診断し、適切な治療を行うことがとても重要です。それによって、今かかっている疾患の悪化を抑えることができ、さらには、新たなアレルギー疾患の発症も予防でき、日常生活をより良いものにすることができる可能性があります。当科では、最新の知見に基づいた根拠のある医療を提供することを基本に、ニーズに合った医療や情報を提供していきたいと考えております。
また、当科は、新しい予防・診断・治療法を開発することも使命としており、厚生労働省、文部科学省などで認められた臨床研究についてご紹介させていただくことがあるかと思います。その際には、臨床研究の内容以外の選択肢についてもご説明し、臨床研究への参加を希望された方のみにご協力いただいておりますので、医療の向上のためにじっくりとご検討いただき、可能な範囲でご協力いただけましたら幸いです。
当科では、ガイドラインに基づいて治療を行っております。気管支喘息の診断と悪化因子の特定には、呼吸機能検査や血液検査、気道過敏性検査などが必要となります。
気管支喘息の治療の3つの柱は、薬物療法、環境整備(悪化因子への対策)、体力づくりであり、これらについて、個々に合わせた指導を行います。
治療に吸入ステロイドを使用する際には、吸入手技指導(スペーサー使用によるpMDI吸入指導、ネブライザーでの吸入指導)を行い、その後もきちんと吸入できているかどうか、定期的にチェックします。
また、難治例、重症例のコントロールのために入院治療も実施しており、比較的長期間の入院が必要な喘息児では、併設の千葉県立四街道特別支援学校と連携・協力し、病院から学校に通いながら、運動療法(毎朝のランニング、特別支援学校に設置された温水プールで週2回の水泳訓練)、心理療法、食事指導、学習、家族指導等を総合的に行っています。
小児科病棟には保育士が連日おり、看護師とともにケアにあたっています。入院中の子供達と四季折々の行事を企画し、入院生活に潤いを与える他、子供達の自主性を育てています。
アトピー性皮膚炎は、痒みの強い湿疹が長く続く病気です。
痒みにより睡眠障害、集中力の低下が起こります。治療の原則は、湿疹の原因となるものをなくし、スキンケアを徹底して皮膚のバリア機能を整え、外用ステロイド薬により皮膚の炎症を抑えることです。これらを行うことにより、皮膚のバリア機能が上昇し、外部からの刺激に強い皮膚になっていきます。
当科では、アレルギー専門の看護師(小児アレルギーエデュケーター)によるスキンケア指導(皮膚の洗い方、軟膏の塗布方法)を行いながら治療を進めていきます。
重症例、難治例には、入院による治療も行っており、比較的長期間の入院が必要な喘息児では、併設の千葉県立四街道特別支援学校と連携・協力して、病院から学校に通いながら、心理療法、食事指導、学習、家族指導等を総合的に行っています。小児科病棟には保育士が連日おり、看護師とともにケアにあたっています。
入院中の子供達と四季折々の行事を企画し、入院生活に潤いを与える他、子供達の自主性を育てています。
食物アレルギーの標準治療は、ガイドラインにあるように、「正しい診断に基づいた必要最小限の原因食物の除去」です。食物アレルギーは、血液検査や皮膚テストのみでは診断できず、血液検査が陽性でも食物アレルギーでないこともたくさんあります。
原因食物を特定し、正しい診断を行うためには、食物負荷試験なども必要となります。ここで正しい診断がされないと、除去する必要のないものを除去し続けることとなり、食生活が不自由になるのみでなく、将来的な食物アレルギーのリスクを高めてしまう危険性もありますので、きちんとした診断を受けることが重要です。
当科では、原則として食物負荷試験による診断を行い、食物除去を最小限に留め、栄養士の指導により栄養バランスを整えながら、定期的に除去解除の可能性を探っていきます。また、食物除去でなく、少しずつ食べながら除去を解除していく治療方法(経口免疫療法)も選択することができます。
アナフィラキシーを起こす可能性がある場合にはアドレナリン自己注射(エピペン)を処方し、アナフィラキシー対策を家庭、学校、園を含めて考えていきます。
湿疹や気管支喘息がある方は、これらの治療をきちんと行うことで食物アレルギーの改善に繋がる可能性がありますので、これらの治療をしっかり行うことが重要です。
湿疹があり、食物アレルギーも疑われる患者様には、まず、スキンケアなどの湿疹の治療を開始し、皮膚をきれいにしてから食物負荷試験などの検査を実施します。湿疹が治ってからこれらの検査を行うと、実際は食物アレルギーではないことがわかったり、食物除去の程度が少なくて済むことがわかったりすることが多くあります。
妊娠中・授乳中のお母様や乳幼児のいらっしゃるご家族へのお知らせです。
妊娠中・授乳中の母親やリスクが高い子供に対する食物アレルギー発症予防のための食物除去(予防的食物除去)は、食物アレルギー発症リスクの高い子供に対する牛乳の除去以外には、不要であることがわかっています。
不必要な食物除去は、逆にその後の食物アレルギーを悪化させる結果になることが多いため、日本でも欧米でも、鶏卵、小麦、ピーナッツなどを含め、予防的食物除去は推奨されていませんので、その子供のためにも、予防的食物除去はしないようにしましょう。
さらに、離乳食の遅れは5歳時の食物、吸入抗原に対する感作を増やすことがわかっており、ピーナッツ、鶏卵、小麦などを早期から摂取開始することでこれらの食物アレルギーが減るという報告もあります。適切な離乳食開始時期は、日本のガイドラインにあるように、生後5~6ヵ月ですので、この時期に通常通りに離乳食を開始しましょう。
食物依存性運動誘発アナフィラキシーは、多くは小学校高学年から中学・高校生に起こる食物アレルギーの特殊なタイプです。原因となる食物を食べるのみでは症状は出現しませんが、摂取後に運動をすると、蕁麻疹、呼吸困難、アナフィラキシーなどが起こる疾患です。当科では、運動誘発負荷試験を行って、原因食物の特定と診断を行い、予防・対策法の指導やアドレナリン自己注射(エピペン)の処方を行います。
アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎は、喘息、アトピー性皮膚炎などに合併することの多いアレルギー疾患です。原因の多くは、ハウスダスト、チリダニ、花粉(スギ花粉、ヒノキ花粉、カモガヤ花粉、ブタクサ花粉、ハンノキ花粉など)、ペット(ネコ、イヌ、モルモットなど)です。当科では、原因となるアレルゲンの検査を行い、原因を避ける生活指導、点鼻薬、内服薬、免疫療法(減感作療法)などによる治療を行います。
ラテックスアレルギーは、天然ゴム製医療用具である手袋、カテーテルなどを繰り返し使用している場合に起こる可能性がある即時型アレルギーの一つです。ゴム製品である手袋やゴム風船と接触して痒みや蕁麻疹が出る場合は注意が必要です。当科では、診断と予防方法、生活上の注意点などについて指導します。
各疾患により、下記の医師が担当します。
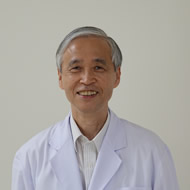
岩本 逸男(いわもと いつお)
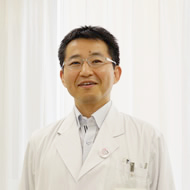
鈴木 修一(すずき しゅういち)
小児アレルギー全般、下記の医師が担当します。
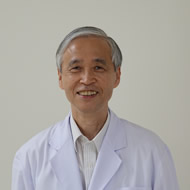
岩本 逸男(いわもと いつお)
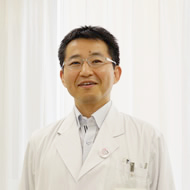
鈴木 修一(すずき しゅういち)

渡辺 博子(わたなべ ひろこ)

佐藤 一樹(さとう かずき)

松浦 朋子(まつうら ともこ)

山出 晶子(やまいで あきこ)

仲村 あずさ(なかむら あずさ)

天野 純(あまの じゅん)
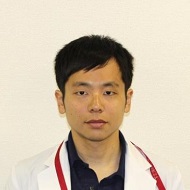
中村 健吾(なかむら けんご)